ページ番号:218486
掲載日:2025年7月18日
ここから本文です。
狭山市
1
| デザイン | 写真 | |
|
|
|
|
説明・由来
狭山市の花(つつじ)、木(茶の木)、鳥(おなが)をモチーフにしました。
設置場所
35°51'23.8"N 139°24'46.4"E
(西武新宿線狭山市駅前)
マンホールカードの発行 (配布場所や在庫状況は、各市町組合へ直接お問合せください。)
有
2
| デザイン1 | デザイン2 | デザイン3 |
|
|
 |
 |
| デザイン4 | デザイン5 | デザイン6 |
|
|
 |
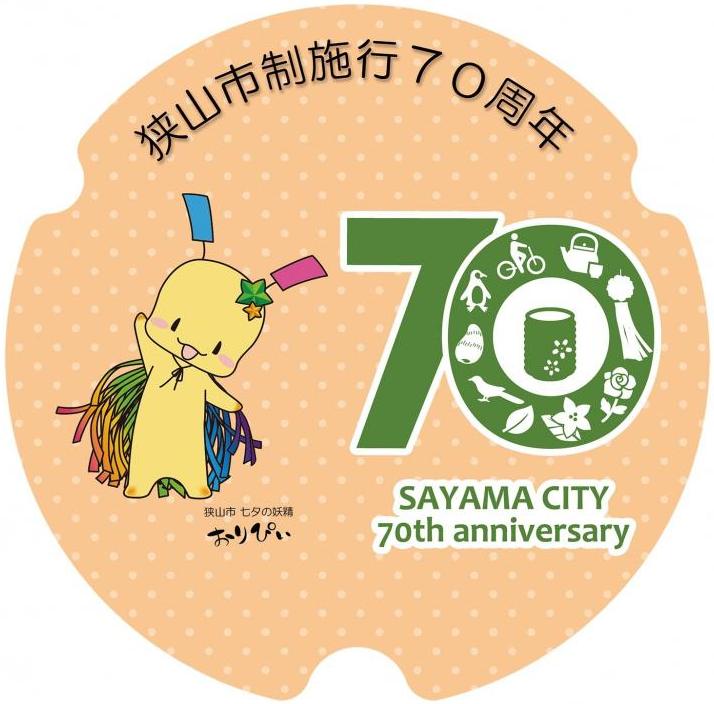 |
説明・由来
狭山市の市制施行70周年を記念して製作したマンホール蓋です。狭山市は、昭和29年(1954年)7月1日に1町5か村が合併し、埼玉県下15番目の市として誕生しました。マンホールには、市制施行70周年のシンボルとして作成されたロゴマークと、狭山市公式イメージキャラクター「七夕の妖精おりぴぃ」が楽しそうにしている様子がデザインを通して表現されています。
ロゴマークは、「70」の数字の中に狭山市を象徴するアイコンを散りばめ、市全体で70周年をお祝いするイメージをデザインしたものです。
※各アイコンは、右上から時計回りに急須、七夕飾り、薔薇(智光山公園都市緑化植物園)、ツツジ(市の花)、茶の木(市の木)、おなが(市の鳥)、里芋、ペンギン(智光山公園こども動物園)、サイクリング(入間川サイクリングロード)、湯飲み
設置場所
(デザイン1,2,3,4,5)
〒350-1305 埼玉県狭山市入間川1丁目1
西武新宿線 狭山市駅 西口ロータリー歩道部分
(デザイン6)
〒350-1305 埼玉県狭山市入間川1丁目1
西武新宿線 狭山市駅 東口ロータリー歩道部分
マンホールカードの発行
無
3
| デザイン |
|
|
説明・由来
【お茶香るまち狭山】
狭山茶は厚みのある茶葉の縒(よ)りと狭山火入れで、甘い香りとバランスの良い渋みが味わえることで有名です。
「宇治の銘茶と狭山の濃茶が出合いましたよ横浜で」「色の静岡、香りの宇治茶、味は狭山でとどめさす」の、茶づくり唄もあります。
設置場所
狭山市南入曽567 入曽駅東口駅前広場
マンホールカードの発行
無
4
| デザイン |
|
|
説明・由来
【鎌倉街道(上道)と化け地蔵と夢地蔵と童】
鎌倉街道(上道)「いざ鎌倉」のために整備された道で、武蔵武士を始め、関東の武士が往来しました。そのため、道沿いには神社や寺院、古戦場が多く点在しています。清水冠者義高が頼朝の追手から逃れ、入間川まで来た道であり、頼朝が信州への狩りに向かった道、新田義貞が「いざ鎌倉」と攻め上った道でもあります。
設置場所
狭山市南入曽567 入曽駅東口駅前広場
マンホールカードの発行
無
5
| デザイン |
|
|
説明・由来
【入曽の獅子舞と童】
毎年10月に金剛院と入間野神社で奉納舞いされるササラ獅子です。金剛院で「揃い獅子」を舞い、本祭では入間野神社で「奉納舞」が行われます。「風雨和順」「五穀成就」「悪疫退散」を願って舞われ、江戸時代の神仏混淆の名残を留める、貴重な県の無形民俗文化財です。入間野神社には宝暦8年(1758)作、獅子舞の絵馬があります。
設置場所
狭山市南入曽567 入曽駅東口駅前広場
マンホールカードの発行
無
6
| デザイン |
|
|
説明・由来
【逃水の里と童】
入曽地区には「逃水」という小字名があります。昔、武蔵野の荒野を、喉を乾かした旅人が水を求めて近寄ると、見えていた水が無くなり、更に遠くに水が見えます。
武蔵野の逃水現象は蒸気説、陽炎説、そして蜃気楼説など自然現象説が語られています。又、武蔵野の逃水としては古歌にも詠われ、詩歌の「ふるさと」として文人墨客の訪問が絶えません。
設置場所
狭山市南入曽567 入曽駅東口駅前広場
マンホールカードの発行
無
7
| デザイン |
|
|
説明・由来
【武蔵野の雑木林と童】
明治の文豪・国木田独歩は「武蔵野の面影は、今わずかに入間郡に残れり」と書き残しています。武蔵野の雑木林は、狭山市水野の里山から、堀兼の上赤坂公園、川越へと続く広大な雑木林です。春夏秋冬、朝昼夜、さまざまな風景が人々の心のオアシスとなっています。珍しい野鳥や野草も多く、市民の憩いの場所でもあります。
設置場所
狭山市南入曽567 入曽駅東口駅前広場
マンホールカードの発行
無
8
| デザイン |
|
|
説明・由来
【伝説の川・不老川と七曲の井と童】
七曲の井は北入曽の鎌倉街道沿い、小字堀難井(ほりがたい)にあり、古歌に名高い「ほりかねの井」の一つといわれています。井戸は漏斗状で水場まで降りる道が七曲りになっている事が名の由来です。平安時代初期に武蔵国府(今の役所)によって掘られたと推定されています。又、日本武尊の伝説もあります。
設置場所
狭山市南入曽567 入曽駅東口駅前広場
マンホールカードの発行
無









